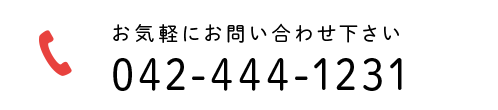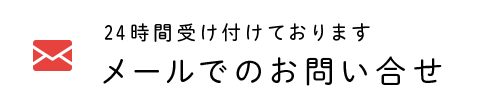それでは1つで5センチ超えたら全部が肝細胞癌かというとそうではなく、肝細胞腫、結節性過形成などの良性病変、さらにはただの血腫なんてこともあります。これらを手術する前に確実に区別する方法は確立されておりません。超音波造影剤を使った検査や造影CTなどで区別する方法が研究されており近い将来で手術前に確定できる日が来るかもしれませんが今のところは手術で切除してみないとはっきりはわからないということです。
では肝細胞種や結節性過形成などは放っておいてもいいのかというと難しいところです。それが5センチを超えてさらに増大していくと破裂し出血を起こす可能性が出てきます。さらに他の臓器を圧迫し嘔吐や下痢、食欲不振などの臨床症状を呈していくことがあります。こういったことを考えるとあまり大きくなるようなら肝細胞腫であろうが結節性過形成であろうが手術を積極的に考えたほうがいいと考えます。
ただし肝臓はご存知のように脆いです。しかも大きな血管がたくさん入り込んでおり、一歩間違えば大出血を起こし最悪の事態になることもあります。手術の際には慎重な操作が必要であり、さらに不測の事態に対し備えが必要です。もちろん経験や技術も必要になります。
ご紹介するワンちゃんは半年前に3センチ大のシコリが肝臓の内側右葉にみつかり、その後一ヶ月ごとの健診をしておりました。その後シコリは徐々に増大し5センチ大になりましたので肝細胞癌を疑い手術にて切除しました。
写真は開腹したところですが、腫瘍が横隔膜に癒着していました。
肝臓の内側右葉の基部に腫瘍がみえます。写真の指先で示しています。その下に見える白いものは胆嚢です。胆嚢は腫瘍に接していたので同時に切除しました。胆嚢を切除してしまっても日常生活に影響はほとんどありません。
肝臓の基部、つまり根元の深い部分に腫瘍が存在しておりましたので視野を広げるために一部胸骨を切開し、さらに横隔膜も切開しています。
内側右葉に流れ込む血管など(門脈、肝動脈、肝管)をはじめに結紮し、次に内側右葉から流れ出る静脈系を結紮していきます。写真は後大静脈と副中間静脈との分岐部を分離し結紮糸を通しているところです。
次に、中肝静脈を後大静脈との分岐部で分離します。細心の注意を払い血管を丁寧に分離していきます。この部位での作業で大出血を起こす可能性がありますので神経を研ぎすまして行います。写真は中肝静脈の分離が終わり剥離鉗子を中肝静脈と後大静脈の間に通したところです。腫瘍が肝臓の基部に迫っていることがわかります。
中肝静脈を結紮した後に肝臓副葉との間を切離し、そして内側右葉を切除しました。
切除した腫瘍です。病理検査の結果は肝細胞癌でした。切除辺縁に腫瘍は認められず、腫瘍は取りきれているという判断でした。腫瘍に切れ目が入っているのはホルマリンが浸透しやすくするためのものです。
ちなみに肝細胞癌が肝臓にあっても特になんの症状も示さないことがあります。それゆえ発見が遅くなり、見つかった時には腫瘍が取り切れないほど大きくなっていたり、主要な血管を巻き込んでしまい完全切除が難しくなってしまっていたりします。定期的に健康診断を受けることが重要です。
犬の肝細胞癌は手術で切除した場合の生存期間の中央値が1460日以上であったのに対し、手術しなかった場合は生存期間の中央値が270日でしたという報告があります。肝細胞癌が他の臓器に転移することはまれなことです。ゆえに腫瘍をしっかり取りきれれば予後は良好です。肝臓に癌ができたからもうダメだとあきらめるのはとってももったいないことなのです。人間の肝臓がんは肝炎ウイルス感染を背景に肝硬変や肝臓がんに発展し予後も様々ですが、犬の肝細胞癌はしっかりとれれば寿命を全うできる可能性が高いのです。